「credit」 実態なき単なる信用力情報が現代経済の基盤 - 前編
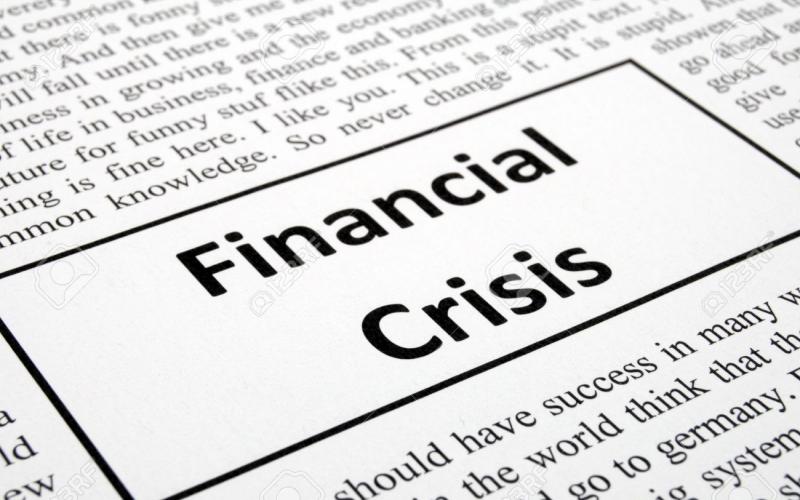
ひと昔ふた昔前、
「日本政府はもっと負債を増やしても、財政破綻することはない。もっとじゃんじゃん国債を発行して市中に金をばら撒き、デフレ不況を脱せよ」
と騒ぐ経済評論家が現れました。
これにノせられたアホ連中が増え、世論を二分しました。
今またCOVID-19騒動により、
「経済活動自粛により国民の生活が危機的状況にある。市中の経済活動も大変追い込まれている。政府はケチなこと言わず、じゃんじゃん支援金を支給せよ」
と騒ぐ連中が増えています。政府が国債を発行して多額の補正予算を組み、国民や自営業者や企業を救うべし、と。……
確かに現在は、そうせざるを得ない緊急事態ではありますが、本来はダメなのです。
財政規律を無視し借金を増やせば、政府も当然ながら破綻します。それは日本政府とて例外ではありません。
如何に日本政府の国債が国内だけで消化されていようとも、そんな事は全く関係ありません。破綻する時はいきなり破綻します。
その辺りの、古典的な経済学講義では教わらない仕組み――敢えて一般市民に教えない(!?)経済学の本質――について、今後何回かにわたって解説したいと思います。
なお、幸田は経済の専門家ではありませんので、細部については誤りがあるかもしれません。
その辺はご指摘願います。
ですが本質的な部分については誤っていない筈ですので、そこを皆さんに知って頂きたいと思います。
現代経済の基盤「credit」
現代経済は、実は「credit」というモノで成り立っています。
creditこそが、現代経済の基盤を成しているのです。
古典的な経済学では、それを教えません。
今、幸田の手元に「入門経済学」(スティグリッツ著)があります。大学の経済学部において、よく基礎テキストとして用いられる本です。
改めてざっと確認しましたが、creditに関する解説が為されていませんでした。
なので、思慮不足の経済評論家等が、
「日本政府は借金増やしても破綻することはない」
などと大威張りで曰うわけです。
いやいや、ンなわけ無いんですよ(^^;
直感で考えても判る事ですよね。やたらめったら借金増やして、破綻しないわけないじゃん……と。
creditとは何か、という経済の本質的な仕組みを知っていれば、「破綻なんかしない」などとアホな事は恥ずかしくて言えない筈なんです。
「credit」とは何ぞや!?
カタカナ表記で「クレジット」です。
皆さんはクレジットという言葉を聞いて、何をイメージしますか。
幸田は小学生の頃、ゲーセンのゲーム機の画面隅に「CREDIT: 1」と表示されていた事を思い出します。
100円玉を追加投入すると、そのカウントが2、3、4と増えるんです。つまり、
「あと何回、ゲームをプレイする権利がある」
という意味だと理解しました。
社会人になると、身近な所ではクレジットカードでしょうね。
カード会社から個々人にそれぞれ限度額が設定され、その範囲内で自由にお金を使う権利を与えられます。
creditとは、経済学用語としては「信用」と訳されています。
これがまた、漠然としていてとらえどころが無い。
和訳した学者が、その本質をイマイチよく理解していなかったのか。それとも充分理解した上で、
「これを一般の人々に教えるのは危険だ」
と判断し、敢えてボカしたのか。……
一体どちらなのかは、皆さんの推測にお任せします。
つまりは「信用力情報」
つまり、creditというのは非常に抽象的な概念なのです。実態がないのです。
その人の立場や見方によって、例えば、
- 貸出限度額
- 信用枠/融資枠
- 返済可能額/返済能力
- 利用可能額
- ……
などと言い換えられるモノが、即ちcreditです。
私達が日常的に用いる「信用」――confidence――という言葉とは、ニュアンスが少々異なります。
まだ、「信用力(情報)」と表現する方が、経済用語たるcreditのニュアンスに近いかもしれません。
実態なき単なる情報
いずれにせよ、creditは実態がありません。
前述のリストを見て頂ければお解りでしょうけれど、「信用力を金額に換算した、単なる情報」に過ぎないのです。
実態なき、ただの信用力情報。――
何と、それが現代経済の基盤なのです。
そして「信用」という言葉の本質通り、
「ひとたび信用が失われれば、たちまちそれは消滅する。泡と消える」
という性質を、本質的に有するわけです。基盤が極めて脆弱なのです。風船でビルの基礎を構築するような状況なのです。
続編にて、さらに詳しく解説したいと思います。




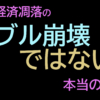
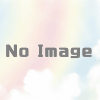







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません